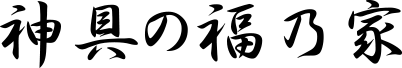神棚にまつわる豆知識
Column
-
神棚 豆知識
神棚に飾る鏡餅の意味と正しい置き方
お正月の神棚に欠かせない飾りといえば「鏡餅」です。
しめ縄や門松と並び、日本の伝統的なお正月飾りとして親しまれてきました。ただ「毎年なんとなく飾っているけれど、実際には意味を知らない」という方も少なくありません。
また「神棚にはどうやって飾るのが正しいのか」と迷う人も多いでしょう。今回は、鏡餅の意味と由来、そして神棚に飾るときの正しい置き方について詳しくご紹介します。
鏡餅の意味
歳神様を迎える供物
鏡餅は、新年に家へ訪れる歳神様(としがみさま)をお迎えし、宿っていただくための供物です。
歳神様は五穀豊穣や家族の繁栄をもたらす神様であり、正月飾りはその神様を迎えるために整えるものです。丸い形の意味
鏡餅は、丸い餅を二つ重ねて作られています。
この形には「円満」「調和」「夫婦和合」といった意味が込められています。
また、昔の鏡は丸く、神聖なものとされていたため「神様が宿る依り代」としての意味も持ちます。二段重ねの意味
二段重ねは「過去と未来」「陰と陽」「月と日」など、対を表し調和を願う形といわれています。
上に小さな橙を乗せるのも、代々(橙=だいだい)の繁栄を祈る意味があります。鏡餅を飾る時期
飾り始め
鏡餅を飾るのは12月28日が最適とされています。
「末広がり」の8は縁起がよく、正月飾りにふさわしい日です。避ける日
・29日=「二重苦」と読めるため不吉
・31日=「一夜飾り」といって神様に対して慌ただしく失礼
そのため、できれば28日までに飾るのがおすすめです。
神棚に飾る場所
神札の前
鏡餅は神棚にお祀りしている神札の前に供えるのが基本です。
お米や塩・水と並べてお供えし、神様に「新年を迎える供物」として整えます。高さのバランス
神棚が小さい場合は、大きすぎる鏡餅は避けましょう。
神札を隠さない程度の大きさで、神様に見やすい位置に供えることが大切です。鏡餅の向き
鏡餅は、神棚に向かって正面を整えて置きます。
神様に対して正しく向くよう意識しましょう。飾り方の手順
1. 神棚を清める
まず神棚を掃除し、お札や神具を整えてから鏡餅を飾ります。
埃や汚れを残したまま供えるのは神様に失礼にあたります。2. 三方や奉書紙を使う
鏡餅は「三方(さんぼう)」と呼ばれる神具の台や、白い奉書紙を敷いた上に置きます。
直接棚に置かず、一枚敷物をすることで「清浄」を保てます。3. 鏡餅を中央に置く
神札の前の中央に、バランスよく鏡餅を置きます。
大きすぎて神棚に合わない場合は、小ぶりのものを選ぶとよいでしょう。4. 橙や昆布・干し柿を添える
本来の鏡餅には橙のほか、昆布(よろこんぶ=喜び)や干し柿(嘉=よろこび)を添える場合もあります。
現代では簡略化されている家庭も多いですが、意味を理解したうえで飾るとより良いでしょう。下げる時期
鏡開き
鏡餅を下げるのは「鏡開き」と呼ばれる行事の日です。
関東では1月11日、関西では1月15日または20日とされています。鏡開きの意味
鏡餅に宿った歳神様の力をいただき、一年の無病息災を願って家族で食べます。
包丁を使わず、手や木槌で割るのが古来の習わしです。
「切る」という言葉を避け、「開く」と表現するのは縁起を重んじるためです。鏡餅を食べる意味
鏡餅を食べることは「神様の御霊をいただく」行為とされます。
お雑煮やおしるこにして食べるのが一般的で、食べることで一年の力を授かると信じられてきました。神棚以外の鏡餅
床の間
神棚がない家庭では、床の間に飾ることもあります。
床の間は家の中で最も格式が高い場所とされ、神様や先祖を迎える場としてふさわしいと考えられてきました。玄関や居間
最近では神棚や床の間がない家庭も増えました。
その場合は、玄関や家族が集まる居間に鏡餅を飾り、歳神様をお迎えするとよいでしょう。家族で飾る意義
鏡餅を飾る作業を家族で行うことには、神様を迎える準備を一緒にするという意味があります。
子どもにとっては「お正月は特別な日」であることを学ぶ良い機会になり、自然と感謝の心が育まれます。まとめ
・鏡餅は歳神様を迎えるための供物
・丸い形や二段重ねには「円満・調和・繁栄」の意味がある
・飾るのは12月28日頃が最適、29日と31日は避ける
・神棚では神札の前に、三方や奉書紙を用いて供える
・鏡開きは1月11日(地域によって異なる)に行い、家族で食べて神様の力をいただく
鏡餅を神棚に飾ることは、新しい年を清らかに迎える大切な習慣です。
意味を理解し、正しく供えることで、神様からのご加護をより深く感じられるでしょう。